弘法大師生誕1250年記念
句碑建立第1回HAIKU日本大賞 春の句

準大賞

(評)名画座といえば少し文学的、芸術的な映画が上映されていたイメージがありますが、そんな映画館はかなり減少しているようです。掲句では、現実に映画館の匂いがショールに残るはずはないので、思い出が残っているということでしょう。誰と観たのでしょうか、青春時代のショールを手にして懐かしく名画を思い起こし、甘酸っぱい感傷にひたっているような雰囲気があります。春の文字がそんな思いを湧きたたせます。
特選

西池冬扇(ひまわり会長)選
(評)和菓子には、視覚的に日本の季節を凝縮させたような美しさがあります。うぐいすもちは鶯の鳴き出す頃、早春の菓子です。求肥で餡を包み、緑色のうぐいす豆の粉をまぶしてあるのが一般的。作者は食べる前にしばしその美しさにみとれました。楕円形に仕上げてちょっと引っ張ったところが鶯の形に似ていると思ったのでしょう。もしかしたら、遍路道で立ちよった茶店かもしれません。「なんとなく」に楽しんでいる感じが楽しく表現されています。

上窪青樹(風嶺主宰)選
(評)嘗ては田植えや稲刈りなどの折に助け合う「結」という制度がありました。近年では農耕機器が発達し、そんな状景はもう見られません。しかし、藍作りという独特な作業では、機械の普及は難しく、今も結という美しいしきたりが残っているのでしょう。結というものは助け合いの精神、日本人の心の美しさの象徴のようなものだけに、心の中にはいつまでも息づいていて欲しいものです。

岩田公次(祖谷主宰)選
(評)このヘルメットは、オートバイや自転車に乗るときのものでなく、仕事の時に着用するものと解釈する方が面白いでしょう。卒業式の日も何時もと同じように、仕事の現場からヘルメットをたずさえてやって来たのです。ヘルメットに焦点を当てて、仕事のかたわら勉学に励んで来た夜学生の姿が活写されています。

鹿又英一(蛮の会主宰)選
(評)四国の吉野川、四万十川には多くの沈下橋(潜水橋)があります。しかし、お遍路さんが遍路の途中に渡らなければならない沈下橋はそれほど多くはありません。そのうち、第十番札所・切幡寺と第十一番札所・藤井寺の間にある沈下橋(川島潜水橋)はたくさんのお遍路さんが渡るようです。この句の場所が、そこかどうかはわかりませんが、景がはっきり見えます。平明で無駄な言葉は一つもなく、一点集中単純化が出来ています。そして、中七の切れ字「や」の力も大きい。充分に言い尽くさない表現の中に奥行きと広がりをもたらし、ゆるぎない完結した世界を作り出しました。

鎌田俊(河副主宰)選
(評)春雨は、陰暦二月末から三月に降る雨のことで、現在では三月下旬から四月にあたります。この頃になると、桜も盛りを迎え、木々の芽吹きも確かで春の深まりを感じます。そのような季感のなか、掲句では求愛期を迎えた栗鼠の機敏な動きに焦点を当てました。最近では、ドローンや小型カメラを用いた撮影により、躍動感ある映像が溢れています。この句からは栗鼠の視点を想起し、春雨の木立や梢を走り抜ける栗鼠の様子が臨場感たっぷりに伝わってきました。「春雨」との取り合わせにより、野生の栗鼠の生態が生き生きと描かれています。

神野喜美女(HAIKU日本理事長)選
(評)日本を「戦なき国」と表現した一句。地球上には、命を奪い合い、街を焼き、破壊し続ける国があります。今も世界には死と向き合う恐怖の中で暮らす人々が大勢います。今年も咲いた「桜」。当たり前でありながら、決して当たり前でない光景。美しさをただ愛でるだけではなく、今年の桜を見られた安堵が漂います。一句一章句で事実を淡々と詠むことで、想いがストレートに届き緊張感のある一句となりました。
秀逸句
(評)「亀鳴く」は春の夕暮れに、雌亀を慕って雄亀が鳴くとされる古くからの季題ですが、実際には亀は鳴きません。その鳴き声を「嬰」ならば聞こえているのではないかというのが作者の洞察です。「嬰」の泣いたり笑ったりすることが、どこかで鳴いている亀に反応していると思うと、無垢な赤ん坊の存在が不思議にも神聖にも思えてきます。
(評)鳴門の一番札所霊山寺から始まり、一周すると約1400キロという四国巡礼の旅。大自然と一体となって真理を追究する旅です。一つのきっかけで心を動かし旅を決心させます。巡り終えた後、また次の巡礼を考える程、生き甲斐となっていく人も数多くいます。いよいよスタート地点。ここまで来た作者の決意がひしと伝わってきます。
(評)一期一会の出会い。遍路旅に限らず、旅には多くの出会いがあります。カップ酒を景色の良い場所に座して酌み交わしているような光景も浮かびます。「行きずり」の上五が、句の景を確かなものにしています。遍路という共通点に話は様々な事に及んだに違いありません。
(評)夕暮れの景を素直に切り取り、読み手の心にお寺の石段を下りる人の後ろ姿を深く刻みます。前を行く人の背中に夕日が射し、桜も昼とは趣を変えます。人がだんだんと去って行く寂しい夕景を「夕桜」に語らせた情趣ある一句です。
(評)上五を「や」で切り、二句一章で格調高く詠んでいます。“浜辺で失くした鈴なのか”“海で出会った人のことなのか”読者を少し心配な気分にさせるミステリアスな一句。それまで聞こえていた鈴の音が今はもう聞こえず、春の潮が大きく速く流れています。読者に色々なことを想像させ鑑賞の幅を広げてくれます。
(評)「下萌える」は冬枯れを経て、野に山に草の芽が萌え出て春の訪れを告げること。大地の息吹を感じ自然のエネルギーに満ちています。「今日といふ光」が、大地から草の芽が萌え出る「下萌え」の力強さを印象づけます。早春の景が鮮やかに切り取られています。
(評)「鷹鳩と化し」は春の穏やかな気配の中では、鷹は鳩のように優しい姿に変身してしまうという春の季語。中国古代の天文学による七十二候のひとつ。現代の最新機器「スマホ」と取り合わせた作者ならではの感性が光る一句です。 スマホを巧みに操る児の様子を、何とはなしに眺めている春の長閑なひとときを感じさせます。
(評)一気に作者の世界に引き込まれてしまう一句。美しい桜貝を見て、「骨片」と詠んだ作者の大胆さに驚かされます。中句を九音にしてまで「恋人の骨片」と詠みました。今はもういない恋人の姿を思い浮かべる優しい女性の姿が垣間見えます。死生観を独自の鋭敏な感性で詠み、何故か郷愁を覚えるような作品。
(評)桜の咲く頃は天候の定まらない日が多く、「花冷」はこの頃に急に寒さが戻り冷え込むことを言います。「花冷」と「ピアス」の似た質感が情景を深くします。星の形のピアスは、作者が恋人にプレゼントしたものなのでしょうか。ロマンチックな気分にさせられます。
(評)世の中を憂うる一人である作者にとっても、大いに癒やされた一日だったに違いありません。陰暦3月21日は弘法大師の忌日で、真言宗の各寺院で法要が営まれます。京都東寺では、4月21日が正御影供とされ多くの人で賑わいを見せます。空海が生きた時代も現代も、その根底においては変わらないものでしょう。いつの世も人間は弱い存在なのかもしれません。
(評)仏は参拝に来たことを喜んで、その人に風を送ったり、生き物を使って合図をしたりするとされます。目の前を飛ぶ二頭の蝶を、父母の遣いだと感じた作者の厚い信仰心が感じられます。「双蝶」はまるで妖精のようでもあり、ひらひらと舞う姿に父母への想いが重なったのでしょう。「安楽寺」は四国霊場の第六番札所。奇しくも「安楽」とは、まるで作者の安らかな心を表出しているようです。
(評)大方の桜が散ってしまった頃に、まだ咲いている桜を深い山などに見出すことがあるのが「遅桜」。昔から人々は、そんな桜に感銘を受け哀れを感じました。この句の「遅桜」は、年齢を経た人物の八十八か所巡りをイメージした擬人化とも捉えることができます。一番札所の霊山寺に在って、これからの秘めた決意が感じられます。
(評)「一陣の風」はひとしきり吹く風のことで、時に大きな風が吹く時があります。その風が去った一瞬の後に、続くようにして桜吹雪が舞う様を写生的に捉えて雅やかな一句。名詞と二つの助詞だけで詠み、「花ふぶき」の平仮名の表記にも作者のセンスが光ります。「一陣」のリフレインが美しく効果的です。
(評)最近、外国人の巡礼者も増え続けている四国遍路。徒遍路は重い荷物を背負いひたすら歩き続けます。その道中、座るのに適した石があれば、つい腰を下ろしてみたくもなります。江戸時代には庶民も巡るようになったという遍路の文化。何百年も続く歴史の中で、人々の信仰の姿が「石の座(くら)」を通して浮かび上がります。
(評)「囀(さえずり)」は春の繁殖期の雄の恋の歌であったり、テリトリー宣言だったりします。“俳句は名詞”と言われるほど選び方、使い方が大事な言葉。一つの助詞と一つの副詞だけで名詞を繋ぎ、流れるような趣のある一句。説明的な用語を使わず詠むことで、一句一章句の説得力のある俳句に仕上がっています。
(評)「花明り」は闇の中であっても、満開の花の白さで辺りが明るく見えること。夜明けのまだ薄暗い中、早立ちの遍路が鳴らす鈴の音が、花の白さで柔らかく感じられたという余情の深い一句です。「花明り」の道をゆるゆると鈴の音を鳴らしながら歩み行く遍路の景は神々しく、読み手にもおごそかな感情を呼び覚ましてくれます。
(評)日本列島は東西に長い故に、桜前線は多少のばらつきはあっても西から上がっていきます。東京まで列車やバスを使うと、それぞれの地方の桜が見えるはず。作者は「桜をよぎり」と表現し一句を際立たせました。上京する作者の想いを「幾千の桜」に寄せ、上京の決意を感じさせる門出の春に相応しい句となっています。
(評)結願の寺、香川県の第八十八番大窪寺。大窪寺の御朱印を残すのみとなった遍路旅。辿り着いた暁には、喜びと安堵感が胸に込み上げ感慨もひとしおでしょう。長い遍路旅の終わりへと近づき、嬉しさに溢れている作者が浮かびます。何かを得るための道、何かを捨てるための道。費やした時間は尊く得たものも大きいに違いありません。「最後のひとつ」に思いが凝縮されています。
入選
夏の句

(評)しっかりと生きて可憐で美しい夏の蝶ですが、1週間もすると死にます。それまでに蜂や蜘蛛におおかたは食われてしまいます。人間も同じでやがて死にます。そして、人間は自分が死から逃げられないことを知っています。しかし、死ぬという大事を棚上げ、あるいは後回しにして日々を送っているのです。
やがて死ぬけしきは見えず蝉の声 芭蕉
芭蕉のこの句を思い出します。自らの生命を生きる孤高の姿があります。
準大賞

(評)「田水張る」は田起こしを終え、畔を塗り終えた田んぼに水を入れることです。田植えまでの数日間、土壌を落ち着かせます。日本の原風景とも言える「棚田」のその頃の夜の景でしょう。信州には、この時期に「田毎の月観月会」というイベントがあります。水を張った棚田の一枚一枚に映りゆく満月を鑑賞するのだそうです。棚田を守り続けてきた農家の大変な労力を想いながら、それぞれの小さな田に浮かんでいる月を「百」のリフレインで見事に描き切っています。
特選

西池冬扇(ひまわり会長)選
(評)大師は高徳な僧に贈られる称号で弘法大師(空海)や伝教大師など六大師が特に有名です。四国八十八か所巡礼は空海の修行の跡をたどる旅なので、この大師も弘法大師のことでしょう。多くの弘法大師立像は右手に錫杖、左手に数珠を捧げています。この句に詠う「祈りの手」とはこぶしを上に向けた左手のことでしょうか。句は上五に「空蝉や」と言い切っています。たぶん大師像のどこかにすがっていたに違いありません。空蝉は蝉の抜け殻ですが、人の世の『虚』であることの象徴とみなされることもあります。作者はその空蝉を通して宇宙の真言へ思いをはせているのかもしれません。

上窪青樹(風嶺主宰)選
(評)高齢の母を想起します。若い頃は活発だった母でしたが、今では外出もできなくなったようです。花を育てることも好きだったに違いありません。しかし、今ではそれもままならず、卓上で水中花を咲かせて、かつてを懐かしんでいるのです。生命をもたない水中花ですが、「咲かせる」という行為に自分の尊厳を守ろうとする矜持が感じられます。そんな母を見守る作者の優しい眼差しが、上七の字余りによって更に高まっています。

岩田公次(祖谷主宰)選
(評)四股名の幟とは、力士名の染められた幟です。そして、七月となれば大相撲の名古屋場所。部屋によっては昔からの馴染みで、地方場所の時に寺を宿舎にします。一句は、大相撲の或る部屋が宿舎としている寺の光景でしょう。はためく幟が、名古屋の夏を象徴しています。簡潔に描いて、余情ある一句となっているところに、作句力を感じます。

鹿又英一(蛮の会主宰)選
(評)「五月」は、野山でも都会でも、樹々がさみどりに包まれる季節です。また、湖沼の光、海の色、そして吹く風の肌触りも、まさに「夏来る」という感覚で、一年の中でももっとも清々しさを覚える季節です。さて、俳句を詠むには、まずおのれの心をひらくことが大切です。自分の心が閉じていては見えるものも見えず、聞こえるものも聞こえません。この句の中七の措辞により、まさしく、思い切り開いた作者のこころが見えるのです。さらに句末の「かな止め」も成功しています。「木漏れ日」と作者の抒情が一体感になっているから「かな」を伴った眼目の「五月」が出現したのです。

鎌田俊(河副主宰)選
(評)天牛の体色を宇宙より賜ったとしたところに、作者の詩的感性が光る作品です。科学の発達により宇宙や地球の起源を探る研究や成果がニュースになることがあります。宇宙への関心が高まれば高まるほど、神秘性は深まっていっているのかもしれません。ここで言う「宙」は宇宙であり、創造主を想定していると思います。天牛の生命を讃歌することは、ひるがえって人間ひとりひとりの存在を尊重し言祝ぐことに通じることでしょう。生命讃歌の大らかな作品と思います。

神野喜美女(HAIKU日本理事長)選
(評)「白雨」は夕方、急に曇ってきて雷鳴を轟かせながら降る雨のこと。強い雨で辺りが白く見えることから「白雨」と呼ばれます。「白雨」と「撫肩」を取り合わせ、具体的に言い切ったところに巧みさがあります。雨が観音像に打ち付け撫肩を洗います。激しい雨の中、対照的な観音像の柔らかい線の美しさを想像させます。
秀逸句
(評)「禅庭花」は、北海道や本州中部以北に咲くユリ科の多年草・日光黄菅のことです。高原や山で、時に大群落となります。寺に咲く山吹色の花が燈明となっているという句は、般若心経の世界観に通じる心のともし火のように感じます。一読、忘れがたい措辞は、詠み手と読み手が共感できます。
(評)豊かな詩情に溢れた心象俳句で、カッコウ、カッコウという艶のある鳴き声が故郷を思い出させます。山や大草原に響く鳴き声は、遠く故郷を離れた作者の心に残っています。「静かな湖畔」や「かっこう」など童謡・唱歌でもよく歌ったので鳴き声は馴染み深いものです。故郷で歌った幼い頃を思い出したのでしょう。望郷の想いが伝わってきます。
(評)「安楽寺」は徳島県上板町にある四国霊場6番札所です。宿坊があり、最近は外国人の宿泊も多いということです。一周約1400キロの四国巡礼の旅は始まったばかり。特に「夏遍路」は通年で一番過酷な旅です。この時でなければ駄目だという強い意志が感じられます。「祈りの永き」の中七が、意味深い教示を示しているようです。
(評)青葉の香りが吹き渡る動物園での一句。子象の愛らしい姿は幾通りにも詠めるでしょうが、掲句は無邪気なさまを「くねらせて」の五音で素直に的確に表現しました。その子象の姿が目に浮かぶようです。季語「薫風」によって、愛らしい子象の姿が何倍にも膨らんだ秀句です。
(評)季語「明易」は短い夏の夜のことです。明け易い夜を案じながら見たオーロラと利尻富士に、思わず歓声が上がったことでしょう。近年、北海道でも観測されていますが、幸運以外の何物でもないでしょう。太陽から飛んできた電子を伴う粒が、地球上の空気の粒に当たって発光するというオーロラ。忘れられない大景を見た感動が伝わってきます。
(評)「青鷺」は鷺の中では一番大きく、羽を広げると1メートルを越えます。田んぼや水辺で餌をとるために絶えず下を向いていて、体型もそのような姿になっています。その青鷺が「空を向く」と表現しています。今の人間世界は憂うる事ばかりで、正義なき混沌の世界に呆れて天を仰いだのでしょうか。独特な視点に読者も納得させられてしまいます。
(評)サギ科の鳥の中でも全身白色が大変美しい「白鷺」。水田に佇む一羽の優美な凛とした白鷺の姿は、「白き孤独」の措辞でよく表現されています。一羽の白鷺にスポットを当てた一句一章句は、「水田」の中のその姿を鮮やかに映し出します。終助詞「かな」で締め、句姿もまた美しい秀句です。
(評)中原中也は、青春の切なさや人生の哀しみを綴った明治生まれの詩人で、繊細な詩を紡ぎ出しました。「山羊の歌」に収められている「汚れつちまつた悲しみになすところもなく日は暮れる」のフレーズは忘れ難いものです。籐椅子にもたれて過ごす時間を三時間と具体的に示して、穏やかな時の流れを表現しました。
(評)放牧中の牛に向かって草笛を吹けば、牛が「も〜」と返してくれるというほのぼのとした一場面。牛たちののんびりとした情景が伝わって来て、開放感のある草原ならではの景が浮かびます。「牛」のリフレインもリズムがあり、楽しく素直な叙述が成功しています。
(評)読み手に様々な想像を与えてくれる句で、奥深い作品となりました。賑わう祭りと作者の複雑な心境。終助詞「かな」の切れが心に響きます。作者の俳境は限りなく広がり、人生の一コマを生活詠の詩として切り取り心に残る俳句としました。作者の深い母への愛情が伝わってきます。
(評)「モンベル」の靴を履くマネキンを見て、「山開」の日だと気付いての作です。モンベルは登山用品やアウトドア用品の人気ブランド。登山好きな作者がモンベルの登山靴を履いて夏山を登る姿が浮かびます。雄大な夏山を想像させる爽快な一句です。心待ちにしていた「山開」への想いと、準備万端で臨む作者の山に対する心持ちが滲み出ています。
(評)四国にはおもてなしの文化があり、その元になったのがお遍路さんに提供する茶菓や食事のお接待です。同行二人と言われるように、弘法大師と共に四国を巡っていると考えられ、お接待は弘法大師への功徳とも捉えられています。次の札所へ向かおうという作者の軽くなった足取りが感じられ、初夏らしい季節感と作者の感謝の思いが伝わってきます。
(評)深い山峡の中、やっと沢まで辿り着いた光景でしょうか。緊張が少しほぐれ、ホッとした中に聞こえてきた「蟬時雨」。いつもは喧騒にも聞こえる蟬時雨も、山の中で沢の水音を聞きながらだと、気持ちよく聞こえたに違いありません。緻密な表現が、自然の実相をくっきりと表出した秀吟です。
(評)生者と死者の境、死亡時刻を詠みこんだ一句です。臨終に立ち会った家族が哀しみの中にいられる時間はあまりにも短く、すぐに次の段階の準備が待っています。何もかもが終わった後、死を振り返られるようになります。あの時が「午前九時」だったことも「青葉」だったことも。こんな青葉の季節に君は逝ってしまう。死という暗さを感じさせずに、哀しみを凝縮させています。
(評)「老鶯」は夏の鶯のこと。人里にいた鶯は夏になると繁殖のため山地に移動し、春の頃よりも大きく奇麗な声で鳴きます。雌を呼ぶためや縄張りの主張らしいですが、詠み手はお遍路さんを誘ってくれている鳴き声のように感じました。疲れの見えるお遍路さんを奥の院へと誘う、応援歌のような鳴き声が臨場感を持って聞こえてきます。
(評)「万緑」とは、草木が見渡す限り緑であること。田舎では整備されていない狭い山道が多いものです。両端に迫る鬱蒼とした緑に「鬱屈」を感じたのも共感してしまいます。見渡す限りの緑の強さに圧倒されます。強烈な生命力に、息が詰まるような苦しさだったのかもしれません。長い長い山道をやっと抜けて、「脱出す」の下五が安堵感を漂わせます。
(評)蝸牛の心情になってその呟きをユーモラスに詠んだ一句です。口語俳句の軽みが出ていて、一度読めば忘れられない俳諧味を出しています。蝸牛は、そんな風に思っていないでしょうが、人の視点からはそう見えます。詠み手の人生の重荷を重ねているようにも見える一句です。
(評)「青柿」は、はちきれんばかりの若さをみなぎらせていますが、熟さないままぽろぽろと落ちることも多くあります。掲句は上五で大きく切って、大胆な二句一章句としました。心象風景を詠んだ一句には、未熟さや若さを象徴する青柿に想いを託した生命への希望があります。疑問形の措辞が読み手にも伝わってきます。
(評)霊場や札所で、巡礼者が鈴を鳴らしながら唱える歌が「御詠歌」。多くは三十一文字の和歌に節をつけて歌います。札所ごとに決まった御詠歌があり、聴いていると心が落ち着きます。インバウンドの影響もあって、異国の人も多いと聞きますが、心の安らぎを求める旅に国境はないに違いありません。
(評)「砥部碗」は、愛媛県砥部町を中心に作られる陶磁器です。やや厚手で丈夫なことから日常使いできる陶磁器として愛されています。夏の季語「甘酒」と「砥部碗」の素朴さとが相まって、その土地の生活や人情までが想像され思わず微笑んでしまう秀吟。お遍路さんへのお接待が身近に感じられ、夏の過酷な旅を励ましてくれたことでしょう。
(評)朝食用に庭のトマトをもいだら、父を思ったという日常の一コマを素直に表現しました。父も家庭菜園をしていたのでしょうか。さっぱりとした風味は、夏の食卓には欠かせません。トマトと父の取り合わせが巧みです。夏の「あさげ」にはいつも並んでいたのでしょう。肩に力の入らない軽みの効いた一句が印象に残ります。
(評)今年の夏は殊更暑く「夏木立」の中、少しでも風の吹く方へ行きたいと願う気持ちが表れています。作者は昔の清涼感ある夏木立に思いを馳せ、この一句となったのでしょう。「夏木立」の青々とした美しい景が、掲句の軽やかな措辞に深い意味を持たせて情感も漂わせています。
入選
秋の句

(評)世界中のほとんどの国の人は虫の鳴くのを右脳で雑音として聞くが、どうも日本人だけは左脳で「声」として聞いているといいます。芭蕉も、「閑さや岩にしみいる蝉の声」と詠んでいます。今年の夏の終わりは、夜お風呂に入っている時に窓を開けて、もう鳴くかと毎日心待ちにしていて、やっと秋の訪れを告げる虫の声を聞きました。虫の声に集中すると他の音は聞こえず、まわりが静かになり、自分独りの世界を楽しむことができます。
準大賞

(評)正月と並び一年の節目でもあるお盆。「盆休み」とあるので、休暇を取って親元に帰ってきたのでしょう。子や孫も集い、親族らが一堂に会した場面が想像されます。一家揃って祖霊を祭りますが、各々が持ち寄ったのが色んな種類のお線香。その場の様々な状況とそれぞれの気持ちが表れています。そんな見逃してしまいそうな所に注目して詠んだ句は、類想の極めて少ない秀句となっています。
特選

西池冬扇(ひまわり会長)選
(評)夕紅葉という下五があるので、秋の夕暮れの静かなお堂でお参りをしているのでしょう。このごろは札所巡りも境内に入る時間制限があるようですが、それはそれとして、夕紅葉には独特の空気感があります。二人連れのお遍路さんを想像するとよい。お堂の前でそっと炎をかばいながら火を点けている様子が浮かぶではありませんか。この句では何ごとでもない動作を、そのまま詠ったところがよい。そこに生じたほのぼのと暖かき景がとても玲瓏な晩秋に似合うではありませんか。

上窪青樹(風嶺主宰)選
(評)オセロは白と黒の石を順次置いて、挟めば自分の石に出来る単純なゲームですが、「覚えるのに一分、極めるのに一生」と言われるほど難解な戦略ゲーム。それを五歳にして大人を打ち負かすとは、凄い感覚の持ち主のようです。ただ、ほのぼのとした季語からすると負けるのを楽しんでいるようでもあり、果たして本気での勝負かどうかは分かりません。ともかく、明るい陽射しの中で小さな子とオセロゲームを楽しんでいる景は正に「秋うらら」です。

岩田公次(祖谷主宰)選
(評)秋刀魚というと煙という感じがしないでもありませんが、「威勢の良くて」と言われると、いかにも生きの良い脂ののった「初秋刀魚」が想像されます。食べ物の句は、美味しそうに詠むことと言われますが、まさに、それを実践された一句かと思います。この秋刀魚、きっと美味しかったに違いありません。

鹿又英一(蛮の会主宰)選
(評)「虫」は、秋に鳴く蟋蟀等の総称です。この題は平安時代にはすでに立てられていて、《わがために来る秋にしもあらなくに虫の音聞けばまずぞかなしき・詠み人知らず・古今集》などと、虫の音が秋の夜の寂寥感を深めていることを詠んでいます。日本人が虫の音を言語脳で聞く世界でも稀な民族であることは知られていますが、それはもう太古の昔からのことなのです。さて掲句、百葉箱があるのだからおそらくは校庭でしょう。見えているのは闇の中に浮かぶ真っ白い百葉箱だけ。そして音は、繁く鳴く虫の音だけです。俳句の鉄則である一点集中単純化と、視覚と聴覚の取り合わせの見事な俳句です。

鎌田俊(河副主宰)選
(評)「ちちろ」はちちろ虫ともいい、こおろぎのことです。秋の夕に鳴きだす虫の声音は、古来より日本人の季節感や美的感覚に影響を及ぼしてきた自然界の音楽です。虫の中でも、こおろぎはとても身近な虫の代表格と言えるでしょう。こおろぎの他にも、ころころ、筆津虫、つづれさせ、えんま蟋蟀、姫蟋蟀など、異称や種類名があります。掲句では、秋の夜長に寂寥を抱く在野の人物を想起しました。厭世的な匂いがあり、さまざまな人間同士の葛藤や争いに絶望を感じているのかもしれません。とはいえ、人間の美点もよく知っているからこそ、人間への期待や理想を棄てきれないでいるのでしょう。作中人物の心の気高さをこおろぎが代弁しているようです。下五「チチロ」は「ちちろ」と平仮名が良いでしょう。

神野喜美女(HAIKU日本理事長)選
(評)「つうと」のオノマトペがよく効いています。作者は都会のプラットホームに立っているのか山間のバス停か、そこは帰路なのか往路なのか、通勤通学か旅の一コマか。作者を取り巻く状況をすべて省略し、ただ「秋茜」の飛ぶさまをクローズアップしています。「時刻表」という馴染みのある素材と季語「秋茜」を取り合わせ、秋の風情を詠み切っています。
秀逸句
(評)胡麻は実が爆ぜたら刈り取り充分に乾かした後、筵の上で棒などを打ち叩いて種を採ります。見掛けることも難しくなった懐かしい光景を切り取った一句。「鼻歌」が心地よく響き、心が浮き浮きするような収穫の喜びが伝わります。秋晴れの山村に住む人々の穏やかな日常があります。
(評)「室戸岬」は空海が修行し悟りを開いた場所です。山上には第二十四番札所最御崎寺(ほつみさきじ)があり、海岸線には空海の修行の場として知られる、御厠人窟(みくろど)と神明窟(しんめいくつ)が並んで存在します。「降臨」は天上に住むとされる神仏が、地上に天下ることを言います。「室戸岬」で「流星の降臨」と詠むことで、空海に想いを馳せている様子が浮かびます。
(評)芭蕉句に「名月や池をめぐりて夜もすがら」があります。晩年の芭蕉が充実の時を詠んだ名吟ですが、掲句はこの句の興趣を彷彿とさせながら、作者によると16歳の時の作だそうです。若い感性の光る作で、清らかな初恋を想起させる瑞々しい句になっています。「池の端」に佇む二人を月が優しく照らしています。
(評)寺社などの銀杏の葉が、金色に輝きながら落ちてくる様は際立って美しいものです。一気に散り尽くしていく様を「浴びている」と大胆に詠んだ作者。それを銀杏からの「接吻」だと捉えた詠みに作者の非凡さが垣間見えます。陶酔した世界に浸っているような印象的な場面が描かれています。
(評)「夜這星」は流れ星のこと。宇宙に散在する物体が地球の大気中に飛び込み、摩擦によって発光する現象です。「草枕」と言えば夏目漱石の代表作であり、草枕の意味は草を結んで枕として野宿することを言います。野宿の遍路が、流星の飛ぶのを見ながら山峡で寝ている姿が思い浮かびます。秋の空を見上げながら、次々に飛ぶ流れ星に目を奪われたのでしょう。「草枕」が遠き道のりの独りぼっちの夜を印象付けます。
(評)「秋深し」は秋もいよいよ深まってきた感慨をいう晩秋の季語です。今盛りの紅葉も、あと僅かで散っていく寂しさなど、秋を惜しむ気持ちが込められています。お大師さんと肩を並べて座る同行二人のお遍路さん。「どっかりと」の副詞が一句を引き締めています。ひと休みと言うよりは、座り込んで暫くは動かない構えです。秋が身に沁みる一日に授かった秀吟と言えるでしょう。
(評)病院ではプライバシーにも配慮して、番号での呼び出しに切り替わっている所が増えています。「秋扇」は夏には大いに重宝された扇ですが、秋風が吹くようになるとパタリと出番が減ってしまいます。まるで、人生にも重なってくるような季語です。壮年期を懐かしむ作者の姿が見えます。
(評)中七の「弾みついでの」が言い得て妙の一句。一区切りついたことで、「秋遍路」に出掛けるという作者。何十年もの重責から解放された開放感がよく伝わってきます。「ついで」と言って遍路旅の気楽さを添えたのも楽しく、肩に力の入らない小気味良さが新鮮です。
(評)歩き遍路ならば約50日は掛かるという遍路旅。旅程には当然、宿泊所も決めなければなりません。候補の一つが「宿坊」です。寺社の境内に設けられた宿泊施設で、座禅、写経、読経などお寺によっては様々な体験ができます。疲れ果てた身で辿り着いた宿坊の夜。「星月夜」は月のない夜、星の光が月夜のように明るい様を言います。「宿坊が眠る」と詠むことで、静かな夜の景を一層美しく描き出しています。
(評)御詠歌を詠う信心深かった祖母の声を思い出しての一句が胸に刺さります。「御詠歌」は仏や菩薩を讃えた三十一文字からなる和歌に節をつけたものです。仏教賛歌として発展・継承されてきました。「御詠歌偲ぶ夜」の措辞に込めた作者の心情が、祖母を偲ぶ家族の初盆の姿を浮かび上がらせます。
(評)つるべ落しと言われる秋の日暮れの淋しさが出ています。親子か、夫婦か、友人同士か「秋遍路」の二人連れは読者の想像に任せながら、寄り添い合う二人をくっきりと浮かび上がらせる巧みな一句です。仲睦まじく遍路道を行く姿が目に浮かびます。一日の疲れが見える時間帯でもあり、「秋遍路」の一抹の侘しさも感じさせます。
(評)四国八十八か所霊場を巡る旅のスタイルは人それぞれです。お遍路さんの格好で、颯爽とバイクで風を切って走っていく様は現代の四国遍路の一面を切り取っています。「白衣菅笠」に着眼し、リズムよく「秋遍路」に着地させています。
(評)「大師」とは人を教え導く偉大な指導者の意味があり、朝廷から高僧に対し贈られる称号。大師の中で最も有名なのが真言宗の開祖・空海に贈られた「弘法大師」です。掲句は「大師のマスコット」に視点を向けたところに新鮮味があります。「秋立つ」は立秋のことで、昨日とは違い秋の気配を感じる一日。爽やかな気持ちが季語に託されていて、杖のマスコットが軽やかに揺れる景が印象的な一句です。
(評)芭蕉句に「萩と月」を使った名句があります。奥の細道に収められている「一家に遊女もねたり萩と月」です。さて掲句、宿坊の「灯の消えゆく」様を表現し、秋の詩情溢れた作品となっています。庭に萩の花が咲き、月が照らしている様子が余情を深め、宿坊の静かな夜を「萩と月」で美しく表現しています。二つの季語が互いを高め合い俳人を魅惑する一句。
(評)平明でどこかユーモアが効いていて、明るい気持ちにさせられる一句です。休んでいたお遍路さんが、背に荷を負ったのか、歩きながらの動作だったのか。見落としそうな場面を詠んで、心に残る軽妙な一句となりました。その瞬間の動作をうまく十七音に仕立ており、秋の長閑な雰囲気が出ています。
(評)作者はヨットを操りながら「天の川」を航海する夢を見たのでしょうか。やや強めの風に撓る「帆柱」の音が、宇宙の静寂の中にあって読者の耳に届いてきそうです。壮大な夢の航路へと導くロマンチックな句で、読者を夢の世界へと誘います。
(評)弘法大師の像の安置された「御堂」に、「夕紅葉」を配した夕暮れの情景が浮かび上がります。秋の日の落ちるのは早いもので、札所巡りの旅もこの日は最後の寺になるのでしょう。切れ字「や」の詠嘆が、しみじみと御堂を見つめる作者の姿を印象付けます。素直な写生俳句の良さがあり、読者に遍路の詩情を享受させてくれます。
(評)秋に収穫した新大豆で作られた豆腐が「新豆腐」。「新豆腐」は、色も香りも新鮮さを感じさせ、新秋の風味として愛好されています。その真っ白な美しい姿に食する為とはいえ、「十字に箸を」入れた様が描かれています。具体的に描写することで、その一瞬の空気感が伝わってきます。一句一章で一気に詠み下し、切れ字「けり」が新豆腐という特別なものに対し、詠嘆の意を添えています。強調し断定したことで何とも言えない叙情があります。
(評)“星を愛した詩人”と呼ばれる宮沢賢治。星を題材にした数多くの作品を生み出し、「銀河鉄道の夜」では「太陽や地球もやっぱりそのなかに浮かんでゐるのです。つまり私どもも天の川に棲んでゐるわけです」と言っています。「天の川」のひとつ“地球”。「降りた星の駅」とは、天の川を形成する別の星から、現世はこの地球に生まれたことを意味するのでしょうか。夜空が美しい秋に相応しいスケールの大きな俳句となっています。
入選
冬の句

(評)仏教の宇宙観はすべての命は大宇宙の微塵でしかないことを悟ること、そしてそのひとつひとつがかけがえのないものとして深い慈しみを覚えること、だと思います。寒の夜空は美しい、その中でも昴と呼ばれるプレアデス星団は肉眼でも多くの星が集まった散開星団です。古くから清少納言が枕草紙で「星は昴」と述べているように、人は身の引き締まるような夜空に昴を仰ぎ見て様々な思いを巡らせました。この句は遍路が底冷えのする夜道を独り辿っているときの感慨だと思うと、しばし心の中まで浄化されていくような冷気を感じます。(西池冬扇 評)
寒すばるのかがやく夜空を見上げたことが、自分の存在を振り返るきっかけになるのでしょう。広大な宇宙にくらべれば、自分という人間に許された時間がいかに有限で儚いものであるか、誰しも一度は感じたことがあることでしょう。作者は人間もまた宇宙のかけらであると方言しています。寒すばると同様に、漆黒の宇宙空間においてもろくも儚い人間でありながらも、瞬く星々にならびたつ尊い光源であると言っているようです。「宇宙のかけら」という表現の中には自尊の心が宿っていると思うのです。(鎌田俊 評)
坂本龍馬が言ったという「人も獣も天地の虫」という言葉を思い出しました。「自分も他の人もちっぽけだけど、広大な宇宙の一部」に違いない・・・。という程の意味でしょうか。
準大賞

(評)「山眠る」は山々が冬の日を受けて静かに眠っているように見えると、山そのものを擬人化した季語です。中国・北宋の山水画家・郭煕(かくき)の「冬山惨淡として眠るが如し」の言葉から出たものです。春が来るのを静かにじっと待っている様が「山眠る」の姿だと言われています。作者の見つめる冬山はまさにそのような山なのでしょう。冬の野山には様々な動物たちが逞しく動いています。そんな存在を感じさせながら、落葉し尽くしてひっそりと佇む雪山の光景が浮かびます。冬の詩情を漂わせ、「山眠る」の本意本情に迫った作風が見事です。
特選

西池冬扇(ひまわり会長)選
(評)お遍路さんの被る笠には「同行二人」や「迷故三界域」とかいろいろ偈(げ)が書いてあります。何かに守られているような気がします。でも、作者はきっと、自然の摂理はそのようなモノでは覆いきれないくらい大きなものなのだ、と雪催いの空を仰いで感じたのかもしれません。同じ帽子でも、兜やヘルメットと違って、菅笠や麦藁帽は平和で、自然の中に溶け込むような感じがします。被っている人を見ると、地球防衛隊の人たちだと思うことにしています。

上窪青樹(風嶺主宰)選
(評)クリスマスを地下バーで過ごすというから独り暮しのようです。地上ではクリスマスソングが流れ、人々が陽気に騒いでいます。哀歓というものはそのときの環境で大きく変わるものです。楽しい時には楽しさが倍増しますが、寂しい時には反比例して逆に寂しさを募らせます。孤独感のある地下バーで聞くそれらの音が、遠い世界の喧騒に聞こえるのも、その所為なのでしょう。

岩田公次(祖谷主宰)選
(評)短日と言われるように、冬は日暮れが格別に早いものです。山間の家ともなりますと、なおさらのことでしょう。加えて「雪催」の天候です。その早さたるや想像に難くありません。灯火に焦点を当てて、冬の山家の暮らしぶりを簡潔に描いた好句かと思います。

鹿又英一(蛮の会主宰)選
(評)「餅搗(もちつき)」「餅配(もちくばり)」という季語は俳諧時代から例句はあります。《もちつきや犬の見上る杵の先 許六》《わが門へ来さうにしたり配り餅 一茶》しかし、「餅」が単独で冬・新年の季語として定着したのは昭和も後半でしょう。元来、餅は祝い事や神事に際しての供え物として作られました。だから、上棟式で撒かれたり、祭礼で配られたりしました。しかし、雑煮にしたり、鏡餅にしたりと餅と正月は付き物です。子供の頃、火鉢を囲んで餅が焼けるのを目を輝かせて待っていました。一番先に焼けて膨らんだ餅を誰が食べるのか、じゃんけんに負けてほっぺたを膨らませた妹を思い出しました。

鎌田俊(河副主宰)選
(評)「暮れ早し」というのは「短日」と同様の意味合いで、冬の日暮れが早いことを言う季節の言葉です。昼は冬至にもっとも短くなり、それからは徐々に時間が回復していきます。冬至を一陽来復とも言います。こちらの句から、クリスマスシーズンなど恋人との電話時間を愛おしむ様子が伝わってきました。最近ではスマートフォンのSNSや通信アプリが活躍していることと思います。掲句はどちらかというと一世代前の固定電話による通話風景を想起しました。郷愁を織り交ぜた恋の一場面としてドラマ性のある作品でした。

神野喜美女(HAIKU日本理事長)選
(評)思いのほか薄く感じられた「夫の掌」。季語「龍の玉」に、妻の優しさが込められています。「龍の玉」はユリ科の「ジャノヒゲ」の実のことで、冬も深まる頃、辺りが枯れている中でコバルトブルーの実をひそかに付けます。まるで涙のようでもあり、一方で緑の葉から覗く実は希望も感じさせます。「握れば薄し」の措辞が悲しみを引き寄せ、快方に向かってほしいという夫への愛情が強く感じられます。
秀逸句
(評)鴨、雁、白鳥などは水に浮いたまま眠ります。「浮寝鳥」は浮寝をする水鳥という意味で使われます。和歌では「万葉集」以来、多くの歌人に詠み継がれて来ました。月の放つ淡い光に、「浮寝鳥」が身を沈め漂っている姿を美しく表現しています。「淡き」と詠んで、まるで万葉歌人のごとく日本的な美に誘い込んでくれます。
(評)遠くても「海鳴り」の聞こえてくる「寒夜」は、宿坊の中にいても不安なのでしょう。「海鳴り」は台風など海が荒れたときに、波のうねりが海岸近くで砕けた際に発する音です。台風や暴風、津波などが襲来する前兆として海上から鳴り響いてくる音を言います。遠くから迫りくるように波の音も風の音も強まってきて恐怖感もあり、明日の天気が気掛かりな夜。そんな不安な高ぶりが如実に描かれています。
(評)現代の暮らしを取り巻く環境は、便利なことが当たり前の生活になっています。ウォーターサーバーもトイレのウォシュレットもボタン一つで適度な湯が出ます。若い人たちにはもう、感謝の気持ちもなくなっているかもしれません。ひっそりと咲いて慎ましやかな「枇杷の花」を対比させて一句を締め、満ち足りた暮らしの中での作者の嘆きのような一言が聞こえてきます。
(評)「煤逃げ」は煤払いの間、どこかへ行ってしまうことを言います。年末の大掃除から上手く逃げ出したと思ったら、置き忘れてしまったスマートフォン。昔ながらの季語と現代の時代の象徴であるスマートフォンの思いがけない取り合わせが、この俳句の妙味です。スマホを忘れて困惑している様子や、逃げ出してしまった罪悪感も滲む平和な日常の一端を見ているような俳句です。
(評)若い頃なら簡単に片付けていたことも、歳を重ねるとなかなかそうもいかなくなってきます。雪国ならではの冬支度の一つのタイヤ交換も難しくなってきたのでしょう。今日は凜と冴え渡った「冬日和」の一日。頼もしくなってきた子供に「タイヤ交換」を頼んだという、日常のふとした場面を詠んで心温まる印象深い一句としました。さり気ない親子愛を巧く表出しています。
(評)「田作り」は片口鰯の幼魚を素干しにしたもの、及びそれを炒って砂糖、醤油をからめて煮たもの。正月の祝い膳には欠かせません。「田作り」の語源は、昔、田の肥料にしたところからとされ、五穀豊穣祈願の意味もあります。田作りをつまみにお酒を飲む父親の姿が浮かびます。「お神酒一本」に、酒好きだった父を想う感慨がひしひしと伝わってきます。
(評)「ICU」は集中治療室。容体の重い患者を24時間体制で観察・治療する部屋です。そんな部屋にあった「小窓」から、外の様子を伺い知ることができ、太陽が覗き込んでいる様子。冬の弱々しい太陽であっても、「ICU」から見える太陽にどれ程癒されたことか、どれ程温もりを感じたことか。「冬日かな」が心に響き、作者の心情がたっぷりと詠み込まれています。穏やかな「冬日」が作者を励ましてくれ、不安な気持ちを和ませてくれたことでしょう。
(評)「小豆粥」は煮た小豆と煮汁を混ぜて炊いたお粥に、餅を入れて食べると厄が払われるという小正月(一月十五日)の風習です。厄払いのつもりが、愚痴ばかりが増えてしまうという一句。作者も元日には、この一年の尊い誓いをきっと立てたことでしょう。誓い通りの日々を送りたいと思いながらも、日常に戻りつつある小正月。「だんだんと」が、この場の雰囲気をうまく醸し出していて家族のやり取りが浮かびます。
(評)「初旅」で作者は今、「銭洗い」で有名な神社にいるのでしょうか。お金を洗うのは古くから行われている習わしのひとつで、お金を洗うと何倍にも増えて戻ってくると言われています。洗って穢れを落とすと、清々しい気分になり新年を迎える気持ちも高まります。「銀貨銅貨」の素材の新鮮さも句を活かしています。「洗ひけり」と過去詠嘆の助動詞で締め、見事な一句一章句となっています。
(評)「おとがひ」は下顎のことです。涙を零すまいと上げた「おとがひ」。涙が落ちるのを見せたくなかったのでしょう。子供を叱った後の子供の仕草を詠んだとも思える一句です。「寒の月」は極寒の寒々とした月を指し、凍て空にあって研ぎ澄まされた美しさを放っています。作者は「寒の月」に心の内を預けて、読者に色んな鑑賞の翼を広げさせています。
(評)「里宮」は本殿が山上にあり、参拝者の為に里に設けられたお宮のことです。驚いたその時の感想が一句となり、「みよちゃん」に平尾昌晃の歌「僕の可愛いみよちゃんは〜♪」と聞こえてきそうです。澄まし顔の巫女が、懐かしい「みよちゃん」。山合の暮らしぶりを郷愁たっぷりに届けてくれて、どこかホッとするような古き良き時代へと連れて行ってくれます。
(評)「また一歩踏みしめ」の措辞が現実感に富み、雪の山中を一歩ずつ踏みしめながらひたすら進んでいく姿を想起させます。淡々と踏みしめる動作が雪の風情を深め、単純明快な描写が冴えています。厳しい自然環境に身を置く人の姿を淡々と詠んだ秀句。
(評)「一人旅」では、夜空に色んな事を思うでしょう。「木枯らし」は、木の葉を吹き散らす強風で、本格的な冬の到来を覚悟させる風です。そんな風の中で見る星は何ともはかなげで、「一人旅」の不安な気持ちも窺えます。さぞかし心細かったと思いますが、瞬く星と共に旅する姿が豊かな旅情を醸し出しています。「空に星追う」の表現がロマンチックに響いてきます。
(評)素材を「綿虫」のみで詠んだ一物仕立ての句であり、五五七の破調の一句。綿虫は腹部に白い綿のような分泌物を付けて空中を浮遊する虫です。冬の風のない日に、ふっとどこからともなく湧きだすように、綿虫は漂い始めます。作者が小さな命を愛おしむ気持ちがよく表わされています。自分に重ね合わせて、命の儚さにも通じているのか余韻の残る俳句です。
入選
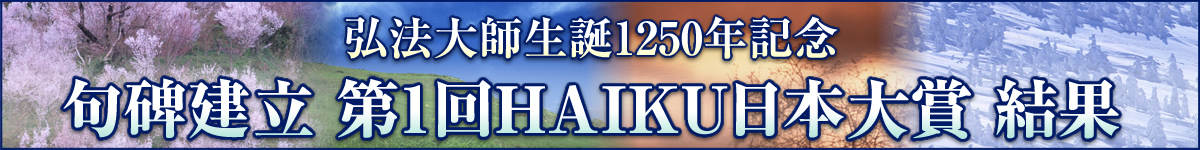
(評)「安楽寺」は四国八十八か所の第六番札所です。「げんげ田」は秋の稲刈り後に種を蒔き、春には絨毯を敷いたように紅紫色の花が咲き乱れる日本の田園の風物詩です。げんげ田から地蔵にクローズアップし、その微笑みが安楽寺へと繋げます。しっかりとした道具立てが成功し、「うふふ」という感じ方、そして表現が、この句を非凡なものにしています。春の田園風景をげんげ田が明るく彩っていて、足取りも軽いお遍路さんの姿が浮かびます。作者の楽しそうな心の内が、お地蔵さんの微笑みとよく似合います。