
HAIKU日本2023全国俳句大会 春の句大賞

(評)「亀鳴く」という季語は、藤原為家の「川越のをちの田中の夕闇に何ぞときけば亀のなくなり」が典拠とされる。実際には亀が鳴くわけではないが、亀が鳴いたと受けとめる風狂や遊びごころをたいせつにしたい。「亀鳴く」という季語には、ユーモアやペーソスをのせた実作例が多い。掲句では、嬰ならば亀の鳴き声が聞こえているのではないかという洞察がおもしろい。確かに、まだ自我や常識に染まっていない無垢な赤ん坊ならば、亀の鳴き声が天使のささやきのように、心に響いてくるのかもしれない。すやすやと眠る嬰が夢を見て笑ったり、泣いたりすることがあるが、どこかで鳴いている亀に反応していると思うと、一段と赤ん坊の存在が不思議にも神聖にも思えてくる。作者の観察と発想力の光る佳吟だ。
珠玉賞

(評)待ち侘びていた春を謳歌するように生き物たちは活動を始めます。木々は芽吹き花が咲き、鳥たちは歌い始め、冬眠していた動物たちは動き出します。春の躍動感が感じられ「ひらがなとなり」が蝶の翔ぶ様を上手く形容しており、たおやかな蝶たちの飛翔が描かれています。一斉に翔び立った、目の前の瞬間を捉えた珠玉な作品です。上五に「いつせいに」と置くことで、春の息吹がより一層感じられます。

(評)「春光を和える」という詩情は、なかなか出てこないものです。作者の深い句心を映発したもの。たっぷりと野菜の入ったサラダボウル。レタスやサラダ菜、ホウレンソウ、アスパラガス、菜の花などみんな春の季語ですが、大きな器の中で踊るように混ぜられている様が浮かびます。感じたままを素直に表現した作者の新鮮な叙情の世界が冴えていて、健康的な一日が快適に滑り出したことが想像できます。
秀逸句
(評)「花冷」は桜の咲く頃の冷え込みを言います。この頃は天候が定まらず、一時的に急に寒さが戻ることがよくありますが、こんな日こそ温かいものが欲しくなります。「蒸し器」に入れられて運ばれてきたその瞬間の場面が浮かび、「花冷」と温かい食べ物との取り合わせが絶妙です。心情を季語に託した軽妙で味のある一句。
(評)「花街」を「かがい」と読ませて定型となる一句。季語「冴え返る」は、立春を過ぎて再びぶり返す寒さのこと。緩んでいた気持ちも引き締まったような感覚があります。芸者屋や料理屋が立ち並ぶ色っぽい「花街」の空がくっきりと読者に届きます。その空に「午後の鳶」がゆったりと舞う姿がクローズアップされます。
(評)春の若草を踏みながら野山を散策する「青き踏む」。爽快な気分を伝える季語です。そんな野原にそよぐ春風を「喉で受く」という、春になった喜びを心から満喫しているかのような一句が心に響きます。季語に続く斬新な十二音の措辞に、春風の優しさが感じられます。
(評)花の終わりの表現は花によってまちまちですが、梅は小さい花びらがぽろぽろと落ちることから「こぼる」と表現され、涙がこぼれる様に似ているからだとも言われています。「たづさへて」と「て」止めにしたのも、この句に詠まれた世界観を美しく昇華させています。梅という素材ひとつに絞り込み、梅にある孤高の美しさを引き出しています。
(評)七・五・五の破調の一句。「初桜」はその年になって初めて咲いた桜の花。開花も満開の時期もほとんどの地域で三月中のこととなり、昔に比べて随分と早まりました。下五の「ハイパチリ」でその場の情景がよく浮かび、読み手を楽しい気分にさせてくれます。校庭に咲き始めた桜をバックに記念の写真を撮る教え子らの弾む心も見えてくる作品です。
(評)ぶんと振るのではなく「ぐんと振る」と詠んだのがこの句の面白いところです。「テニス部が打つ」としたところに新鮮さがあり、その光景がよく見えてきます。「ぐんと振る」景は力強く、日焼けした若者たちの姿がイメージできます。春の陽気の中での楽しそうな部活動の様子を伝え、青春真っただ中にある眩しさを引き出しています。
(評)石川啄木は情熱の赴くままに各地を転々とし、貧困と病気に苦しみながら短い人生を終えました。歌人・詩人として明治時代に活躍した人物ですが、啄木の短歌は三行書きのスタイルで、身近な現実を詠み己の人生に迫りました。三行の「解雇通知」に啄木を重ね合わせ、解雇通知さえもそれがどうしたという作者の余裕が感じられます。
(評)「麦を踏む」姿は日本の長閑な原風景の一つと言えます。昔を忍ぶ日本の農業の細かさですが、「麦の影視て」には体験した人でなければ言えない重みがあり、土の感触さえ読者に届けてくれます。「麦」のリフレインが余情と深みを感じさせ趣のある一句です。
(評)「かひやぐら」は蜃気楼のことで、地上の物体が浮かんで見えたり、遠方のものが近くに見えたりします。作者にとって父からの謝罪の一行は思いがけない出来事だったのでしょう。内容を作者は明らかにせず、読者は考えさせられてしまいます。作者の巧みなところです。謝罪の一行は現実だったのかを含めて、読み手の想像力を掻き立てます。
(評)今年の「盆梅」に心から満足している様子が覗える作品です。色彩豊かに詠んで、「茶の緑」と対比させた個性的な一句に惹かれます。梅の花の馥郁とした香りに包まれた席でいただく抹茶の味はまた格別でしょう。丹念に育てられた「盆梅」の姿を、たくさんの色を並べて詠み俳句に遊ぶ作者。色とりどりの梅を想像するだけで、読み手にも作者の心持ちが伝わってきます。
(評)今は菜の花でいっぱいでも母の畑であった頃は、きっとたくさんの野菜を育てていて、その思い出も懐かしく蘇っていることでしょう。今を盛りと咲いている「菜の花」。きっと母もそれを見て喜んでくれているに違いないと、そんな気持ちにさせてくれる優しい一句です。母を想う風情が淡々と伝わってきて、淋しさと温もりの入り混じった心を揺さぶられる秀句。
(評)「曇天」の日のその湿りの中で見る「山桜」。しっとりを略した「しとり」の副詞が効果的です。古より詩歌で詠まれてきた山桜の気品のある美しさを、より一層浮かび上がらせてきます。山桜の姿を、まるで山水画のように上手く仕立てています。艶やかな若葉と共に開花した一重のピンクの花が静かに山里に佇んでいます。
(評)雄の縄張り宣言や雌を誘うラブコールで、様々な鳥たちが鳴き交わす春。春の訪れを喜ぶかのように、一斉に賑やかになったのでしょう。「囀の庭」と詠むことで、作者の庭にも鳥たちがひっきりなしに立ち寄っては、美しい声を聞かせている様が届きます。鳥たちに思わず口笛で応える作者。うららかな春の日のひとときが鮮やかに切り取られています。
入選
HAIKU日本2023全国俳句大会 夏の句大賞

(評)夏蜜柑は、初夏に食べごろを迎える柑橘で、果実は大きく、酸味が強いのが特徴です。祖父の手にある夏蜜柑は、いましがた庭の木から捥いできてくれたものでしょうか。夏蜜柑に初夏の日があたり、まばゆいばかりに輝いて見えるさまが一句に表現されています。「プリズム散らす」という中七の措辞がとても新鮮です。この表現の中には、夏蜜柑を眩しく見る作者の感動だけではなく、夏蜜柑を採ってきて孫が自然に触れる機会をつくり新しい物事を教えてくれる祖父への畏敬の念も込められているのでしょう。夏蜜柑の酸っぱさを教えてくれた祖父とのかけがえのない思い出の一齣が、光褪せることなく一句のなかに息づいています。
珠玉賞

(評)「出目金」の大きな二つの眼に、心が宿っているという着眼点がユニークです。そんな発想をする作者の人情や人柄までもが楽しく想像されます。確かにキョロキョロ動く出目金の眼はそれぞれに違った動きをしますが、こんな見方をする作者の独特の感性が俳諧味たっぷりの句を生みました。

(評)「辻回し」と言えば日本三大祭りのひとつ、京都の祇園祭の山鉾巡行の一コマ。掲句は巨大な山鉾の進行方向を変える「辻回し」の迫力を言い得て妙。大通りでは豪快に回す様が見られる一方、小路では指示役の誘導で微調整を繰り返しながら向きを変えます。祭り囃子ではなく「炎天の声」で、その場面を彷彿とさせます。暑さも吹っ飛ぶ程の景を見事に描き出し、その緊張感が伝わってきます。
秀逸句
(評)印象派の巨匠・モネが好んで描いたのが「睡蓮」です。熱帯原産の多年生水草で赤、白、黄の可憐な花を付けます。水面で微かに揺れた睡蓮を見た作者の確かな写生の眼が感じられ、読み手にその場面を明瞭に伝えます。沼や池の穏やかな水面に浮かぶ睡蓮の美しい姿が浮かびます。
(評)鬼ごっこをして遊んでいた子供たちが、だんだんと家に帰っていく。そんな夕暮れ時の光景が浮かびます。鬼役の子だけが残ってしまった昭和の残影のようなノスタルジーが漂い、完了の「ぬ」で止めて効果的な一句に仕上がっています。取り残されたように夕焼けの街に立つ、一本の「鬼の木」。一つの物語のラストシーンを思わせるような一句です。
(評)「夏つばき」は夏に椿に似た五弁の白い花を咲かせ、別名「沙羅の花」とも呼ばれます。散り敷かれた様が見事に描かれた一句一章句で、大地に還った花を「足の踏み場もない」と詠んだ作者。「夏つばき」に話し掛けるように詠んだ一句は、ユニークさを感じさせます。目の前にある実景を詠んだ写生句の魅力に溢れています。
(評)夏の夜を楽しむ様が臨場感を持って詠まれています。一山を包み込むという大花火はどれ程のものなのか・・・。「山ひとつ包み込みたる」の措辞が読者の想像を掻き立てます。夜空に輝く絢爛たる大輪の花火は言うまでもなく、打上げの迫力ある音や地面を這う振動なども伝わってくる豪快な一句。
(評)作者は20代の若い俳人。現代にあってもレトロファンは多くいて、NHKのラジオ深夜便などでも、ドーナツ盤での音楽を楽しむコーナーがあります。「ドーナツ盤に落とす」の措辞によって、ゆったりと流れる至極の時間が伝わってきます。部屋の窓を開けて涼しさを感じながら詠んだ味わい深い一句です。
(評)何とも言えず滑稽味たっぷりの秀作。主役はオレだと言わんばかりに置かれた一品の「面構え」。荒々しい風貌が「文句あっか」と言っているかのように思えたのでしょう。味は“夏の河豚”と呼ばれるほどの美味。「こう見えても、すこぶる美味しいんだぜ」と我が身を誇る「鬼虎魚」の声が聞こえてきそうです。
(評)「コイン」と「汗」の取り合わせがとても良く、素直な詠法が魅力を放っています。「コイン」の落ちる音とポタポタ落ちる「汗」の音。猛暑の中やっと自販機を見つけたのか、どこかホッとしたような感覚が漂います。五感を研ぎ澄ませ、音をリアリティーを持って詠んだ味のある巧みな作品です。
(評)シャツの柄が少々派手目ではないかと、気になりながらサングラスを掛けて外出。少々弱気になる心をカバーし、数倍強くしてくれる代物が「サングラス」。解放感ある夏のお洒落に挑戦する「八十路」の微妙な心理と実感で、日常のことをさらりと詠み上げた俳諧味のある秀句です。
(評)“足”が付くので樽回しなどの足技を特技とする芸人と想像できますが、人気はまだまだなのでしょう。「薄い背」がそのことを物語っているようです。「足芸人」の哀愁が一句の中に漂います。背中を丸めて髪を洗う芸人への労りの心情が見て取れ、優しさに溢れる一句となっています。
(評)「婚約す」という素敵な言葉が印象的な一句。汗の匂いが強くなる夏の身だしなみとしても使われることから、夏の季語である「香水」を思い出と共に詠んだ句は、季語の持つイメージを遥かに超えた優美な響きを醸し出しています。人生の節目となった夏を蘇らせるロマン溢れる秀句。
(評)「夕立」と「ポマード」の斬新な取り合わせが魅力の一句。「ポマード買うた」の優しい響きが懐かしさをより一層深めます。ノスタルジアを感じさせ、「ポマード」の懐かしい響きに昔の父親像が蘇ります。古き良きものへの哀愁と父を想う心情が相俟って、印象深く心に刻まれる秀句です。
(評)海の月という字のイメージだけでもロマンチックな「海月(くらげ)」。ふわふわと漂う様は儚く美しく、見ているだけで癒やされます。「さみしくて空が見たくて」の十二音がとても美しく響き、読者の心を詩情世界へと誘ってくれます。「海月」の気持ちを慮って、見つめている作者の姿が浮かびます。
(評)「ぬばたま」はヒオウギの種子のこと。丸く光沢のある黒色の種はミステリアスで、「夜」「夕」「闇」「髪」など黒い色に関連した語にかかる枕詞です。そんな闇夜こその「螢」。螢の光る様には様々な表現がありますが、「燃ゆる」とはなかなか表現しないもの。作者の特別な想いが託されているようです。「ぬばたま」と相まって艶やかさを漂わせています。
入選
HAIKU日本2023全国俳句大会 秋の句大賞

(評)ロシアのウクライナ侵攻は泥沼の様相を呈しています。何のための戦争なのでしょうか。こんな世界情勢と取り合わせるのは、昔ながらの暢気さのまま、収穫を待つ秋の田に佇む「案山子」。「案山子」は知らぬとした一句には、作者の様々な思いが込められていて、危ない時代に生きる不安を際立たせています。
珠玉賞

(評)猛暑を通り越して、散歩の途中の「ブルドッグ」も息を弾ませることも無くなったのでしょう。「足取り軽く」と感じた作者の弾んだ気持ちが現れています。「新涼」と「ブルドッグ」の取り合わせに妙味があり、清々しさを満喫する作者の足取りも自然と軽くなっていく様子が伝わってきます。

(評)「菊人形」は秋の風物詩の一つと言えます。最近は昔ほどの派手さはなくなったものの、菊師の情熱は連綿と受け継がれています。しなやかで作業しやすい「小菊」は、人形に着付ける際に用いられます。展示の期間に開花を合わせるための苦労も大変なことでしょう。そんな苦労をねぎらうかのような作者の優しさが感じられる一句です。
秀逸句
(評)「震災記念の日」は、大正12年9月1日午前11時58分に発生し関東一円で莫大な被害を被った、関東大震災の犠牲者の霊を弔う日です。可愛い孫の髪を梳いてやりながら、この日に当たることを思い出したのでしょう。「この子たちの時代がどうか平和でありますように」と願う作者の横顔が見えてきます。
(評)冬に向かっての支度は、深い山々ではことさら大変でしょう。晩秋の趣きが残る「渓谷」は、季節が進むにつれ枯色になります。「墨絵ぼかし」が目の前の景を読者に思い浮かばせ、観察眼の優った写生俳句となっています。墨絵の持つ濃淡の美が、晩秋の佇まいを伝えてくれます。
(評)配合と言うよりも二物衝撃のシュールな作品。「もらい」のリフレインが面白味を出した一句です。若さ溢れる詠法で、作者のこれからの俳句が大いに楽しみです。作者のウキウキした気持ちが伝わってきて、読み手も楽しい気分にさせてくれます。
(評)「風は秋」としたことで余情も深みも増しました。流れるようなリズムで作者の心境を表わし、「秋」の言葉から感じる侘しさや寂しさよりも、楽しみにしていた秋がやってきたことを喜ぶ作者の姿が見えます。自らの人生に対する感慨が伝わってきて、味わい深い境涯俳句となっています。
(評)「立札」が自分の農園であることを示している貸し農園を思い浮かばせます。消えやすく、儚いものにたとえられる露。殊に「朝露」は日が昇ると間もなく消えてしまいます。農作物や辺りのもの皆が、露に濡れた清々しい朝の瞬間を詠んだ秀吟となりました。
(評)晩秋に夜分寒さを覚えるのが「夜寒」。普段通りの暮らしを詠んだ然り気ない一句に、作者の生活感が出ています。日常の出来事が何か捨てがたいような哀愁を漂わせています。終助詞「かな」が一句全体を包み込んで、効果的な秋の一句となりました。
(評)「割算」が苦手な子供は、「西瓜」を割るときに苦労するのかもしれません。等分に分けるのは、なかなかの難問です。掲句は一句一章句として捉えることが出来、作者の優しい眼差しが感じられます。発想に意外性と面白みがあり、読み手にもほのぼのとした景を思い起こさせます。
(評)重厚感ある様からは想像できないほど、高く透き通った音色が愛される南部鉄器の風鈴。音色が長く鳴り響くのも魅力のひとつです。季節は秋になって涼しさを感じ始めた頃、その吹く風を「涼新た」と言います。中七の「風の調子や」に妙味があり、初秋の冷気の心地よさが漂ってくるようです。
(評)「つづれさせ」は綴刺蟋蟀(つづれさせこおろぎ)のこと。りーりーりーと鳴く声を昔の人は「肩刺せ、裾刺せ、綴れ刺せ」と聞いて、着物の綻びを縫い直せと教えているのだと言います。「たつき」とは生計のこと。「メモ紙」もチラシなどを使っていると思わせてくれます。冬に向かっていく秋の寂しげな情趣を詠んだ一句で、慎ましやかな暮らしぶりが垣間見えます。
(評)なかなか見られない猟師の捌きの場面を想像させ、読者をゾクッとさせるものがあります。「猪(い)」は秋の季語。深まる秋の中、狩猟の場面とその後を連想させて、現実以上にリアリティのある迫力の作品となっています。「蛇口の音」の激しさを詠んで、獰猛な猪の姿を浮かび上がらせる技の上手さがあります。
(評)「稲の波かぶりて遊ぶ雀かな」「いそがしや昼飯頃の親雀」など子規は雀の句も多く残しています。忌日は9月19日。寝たきりになった子規の目を四季折々に咲く草花や、庭にやってくる鳥たちが大いに楽しませたことでしょう。そんな子規の目線で詠んだような一句が心に沁みます。「かな」の詠嘆がこの上なく優しく響きます。
(評)大胆で粗削りなところが魅力の俳句です。副詞としての「唯」が効いていて、「柿落とす」のは「からす」のみが知ること。下五の強調の助詞「ぞ」で切ったのも効果的な一句です。からすの他は誰も知らないに違いないことを強調し、作者の気持ちを込める働きをしています。
入選
HAIKU日本2023全国俳句大会 冬の句大賞

(評)ポインセチアは、観賞用に温室で栽培され、クリスマスのころに枝先の葉が緋紅色になります。俳句では、鮮やかな紅色の植物を炎のように燃えているようだと形容する表現技法があります。紅葉や鶏頭など、さまざまな植物の印象鮮明な色彩を幾度となく組み合わせて詠まれてきていますので、もはや共有の財産の表現です。掲句では、「ポインセチア燃ゆ」に対して、「合鍵を返却」という措辞をもってきています。これにより、合鍵を返却するに至った事情や、合鍵を返却してからのこれからの展望など、合鍵返却という一事が読者の内にストーリーを喚起し、想像を膨らませます。季語が作中人物の心情を象徴して訴えてくるようです。合鍵返却以降に、もっと素敵なドラマが待ち受けていることを予感させる、向日性のある作品で、まるで小説の一場面を思わせます。
珠玉賞

(評)関西ダービーとなった今年の日本シリーズの五試合目を思い出します。阪神のルーキーが低めの球を弾き三塁打を放って、勝負を決めました。そのままの勢いで阪神は38年ぶりの日本一。こんな熱闘の場面を蘇らせてくれる俳句。「やや低めにて」の中七がこの句を際立たせており、緊迫の一瞬をさらりと伝えています。

(評)初冬の頃、降ったりやんだりする通り雨が時雨。伝統的に風雅な趣や無常の嘆きを含みます。時雨の降る日、出棺時に霊柩車が長いクラクションを鳴らすと、それが故人との最後の別れになります。見送りの列に遠ざかるクラクション。「しぐるるや」が一層の悲しみを誘い、哀切に満ちた余韻のある一句となっています。
秀逸句
(評)季語でいう「蕎麦湯」は、蕎麦粉を熱湯で溶かし甘みを加えたもので、現代の蕎麦屋で出されるものとは異なります。蕎麦を茹でたときの汁は、蕎麦に含まれているタンパク質が溶け出しているため白くて少しとろみがあります。白濁した齢(よわい)に馴染むとは、その人の人生をも語ってくれているような何とも言えない味。一口飲めば冷えた体が暖められ、染み渡っていく様が想像できます。
(評)川や池などに棲む「寒鯉」は、水温が低いため泥の中に潜ってじっとしていることが多いもの。その寒鯉が人影に動いたような、その一瞬を捉えての作。かすかな動きをすかさず切り取った詠み手の感性が光ります。「微動」が極寒の水に晒されて生きる「寒鯉」の厳しさをよく表しています。
(評)トラクターなどの轍の跡に、「天水」が溜まっている冬の一日の光景を詠んだ秀吟。自然への畏怖の念が感じられます。淋しい田園が思い浮かび、役目を終えた「冬田」の景がしみじみと伝わってきます。雨空の日には冬田は一層侘しさを増し、見つめる作者にも寂寥感が去来したことでしょう。
(評)猛暑に続いた秋はあっという間に終わり、今年はすぐに冬がやってきました。セーターやコートなど嵩張る厚物がずらり並んで、部屋は衣装替えの真っ最中。冬がやってきた実感を「ずらり厚物」の中七の措辞が言い得て妙です。誰しもが実感し、共感を呼ぶ一句は「冬来る」の季語で温かな余情が広がります。
(評)廃止となった「ケーブルカー」の跡のみ残る冬の山に、盛況だった過去を想うと淋しさもひとしお。山は何事もなかったかのように静かに眠りにつきます。落葉しつくした山々が冬の日を受けて眠っているかのように見えると、擬人化したのが「山眠る」の季語。この季語が雄大な冬景色の中、ピタリと収まっています。
(評)思わず「虎落笛」の「ひゅ〜」の調べが聞こえてきそうです。怪談に付き物なのが、ひゅーひゅーという効果音。その音が「虎落笛」であるという作者の発想が楽しい一句。あのおどろおどろしい音が「虎落笛」と重なり、妙に納得させられてしまいます。「怪談」と「虎落笛」の取り合わせに意外性がありウィットに富んでいます。
(評)「六つの花」は美しい結晶から名付けられた雪の異称。「担任」の先生と「僕」の関係に何があるのか、深読みさせられてしまうミステリアスな一句。何やら正反対の場所に居て、別世界の僕には雪が舞ってる様子。寒さの中、侘しさと哀愁に包まれる「僕」の姿が印象深く、破調の一句に作者の感性が冴えています。
(評)「ゆっくり」バターが溶けていく様を一句の眼目にして、「立冬」と取り合わせました。ゆったりと料理をしている主婦の余裕が感じられる生活詠の中に、俳句の詩としての普遍性が漂う感性の一句となっています。「溶けて」ではなく「丸くなる」と形を詠み読者に興味を抱かせます。
(評)一人だけの食事は味気ないもの。だんだんと煮詰まってくる「一人鍋」に「寂しさ」を感じたという作者。鍋で身体を温めながらも感じる寂しさが、読者にも伝わり共感を呼びます。「煮詰まつてくる」が作者の心の動きをよく表わしていて、現代社会の一面を見る思いがします。
入選
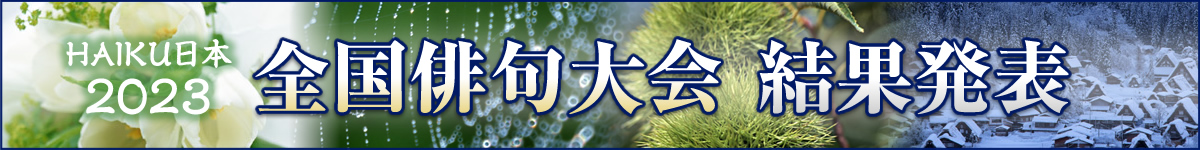
(評)「俳句歳時記」において、一月から十二月までどの月も季感を有する詩語として載録されています。一句にどの季語を持ち込むかは、作者の創意工夫の対象です。ほかの季語でも成立する、ほかの季語のほうがもっと句意が豊かになる、と読者が思える隙がうかがえると、作品の訴える力が弱くなってしまいます。掲句の「八月」に触れ、とても有意な一句になっていると感銘を受けました。「八月」は日本の歴史的転換点の意味合いがありますので、季節の時間性を超えた象徴詩の世界として掲句が屹立しています。証言台は、裁判において証人や当事者が証言をしたり、質問に答えたりする場所です。歴史性を呼び込む「八月」を配することで、事象の報告にとどまらない、緊張感ただよう象徴詩となっています。